夜行快速列車の代名詞、青春18きっぷユーザーご用達の「ムーンライトながら」。夜行列車が次々と消えていく中で、臨時列車に格下げになりながらも、今のところ青春18きっぷシーズンを中心に運転されています。ところが、運転日数が年々減っているうえに、使用している185系車両も寿命が近く、予断を許さない状況です。今後、「ムーンライトながら」はどうなってしまうのでしょうか? いろいろな角度から分析してみました。
年々運転日数が減る夜行快速列車「ムーンライトながら」
青春18きっぷユーザーや乗り鉄の方なら、知らない人はいないであろう夜行快速列車「ムーンライトながら」。古くは、大垣夜行と呼ばれた普通列車にルーツを持つ「ムーンライトながら」ですが、最近は運転日数が減少傾向にあります。
夏(7~8月)の運転日数は以下のように推移しています。
- 2017年夏: 30日
- 2018年夏: 23日
- 2019年夏: 17日
2019年の夏は、ついに7月の運転がなくなり、8月1日~17日(東京発)、8月2日~18日(大垣発)の17日のみの運転となってしまいました。
ムーンライトながらといえば、青春18きっぷユーザーに大人気の列車。特に夏の運転日は、早々に指定席券が売り切れてしまうほどの人気列車になっています。
そんな人気列車なのに、なぜ運転日数が減っていくのでしょうか? そして、今後、「ムーンライトながら」はどうなってしまうのでしょうか?
「ムーンライトながら」、1列車で売り上げたった30万円!?
人気列車にもかかわらず、運転日数が減っていく「ムーンライトながら」。その理由の一つとして、JRにとって「もうからない列車」であることがあります。
というのも、ほとんどの乗客が青春18きっぷを利用して乗車するためです。
ご存知の通り、青春18きっぷは日本全国のJR線に乗車できるフリーきっぷです。JR各社で売り上げの配分が決められていると思いますが、「ムーンライトながら」に青春18きっぷで乗車する乗客が多いからといって、ムーンライトながらを運行するJR東日本とJR東海の取り分が増えることはなさそうに思います。
そうなると、「ムーンライトながら」の純粋な売り上げは、指定席券×乗車人数、ということになります。
ムーンライトながらの指定席券は520円、定員は約650名(185系10両編成)ですので、
520円 × 650名 = 338,000円
となります。
10両編成の列車を夜通し走らせて、売り上げが30万円ちょっとでは、JRにとってはおいしくない列車ですね。

もちろん、青春18きっぷもJRの売り上げになりますし、「ムーンライトながら」に乗車するときに、日付が変わる小田原駅(下り)、豊橋駅(上り)までの乗車券を買う人も多いでしょうから、実質的な売り上げはもっと大きいはずです。
3割くらいの人が、東京~小田原の乗車券(1,490円)を買うとしたら、
1,490円 × 220名 = 327,800円
となり、これに指定席券の売り上げを加えて、約65万円+青春18きっぷの実質売上、といったところでしょうか。
「ムーンライトながら」のために深夜の客扱いが必要
「ムーンライトながら」を運行するコストが安ければ、実質的な売り上げが少なくとも、利益は出るでしょう。
「ムーンライトながら」のコストとしては、運行にかかわる経費として、乗務員(運転士・車掌)の人件費や車両を運行させるための電気代などが挙げられます。
さらに、忘れてはいけないのが、ムーンライトながらが深夜に停車する駅の客扱いに関する費用です。
ムーンライトながらは、上り・下りともに、静岡県内の主要駅に深夜時間帯、つまり、終電後から始発前の時間帯(おおむね午前1時~4時頃)に停車します。時刻表にも記載された正規の停車駅ですので、当然、これらの駅での乗り降りができます。つまり、駅には、この列車に対応するための駅員を配置しておく必要があるわけです。
現在、唯一、定期列車として運転されている寝台特急「サンライズ出雲・瀬戸」(静岡県内は併結されて1列車として運転)がありますが、深夜時間帯の停車は、浜松駅を除けばありません。
| 停車駅 | ムーンライト ながら 下り |
ムーンライト ながら 上り |
サンライズ 下り |
サンライズ 上り |
|---|---|---|---|---|
| 沼津 | 01:07着 01:08発 |
03:05着 03:21発 |
23:39着 23:40発 |
05:26着 05:27発 |
| 静岡 | 01:48着 01:50発 |
01:52着 01:55発 |
00:19着 00:20発 |
04:38着 04:40発 |
| 浜松 | 02:46着 03:02発 |
00:46着 00:55発 |
01:11着 01:12発 |
通過 |
2019年3月ダイヤ改正の沼津、静岡、浜松の3駅の時刻表はこのようになっています。
ムーンライトながらの太字で示した停車駅・時刻が、終電後~始発前にあたり、しかも、定期列車のサンライズ出雲・瀬戸の到着・発車時刻とも大幅にずれています。
特に、午前3時台にムーンライトながらが停車する沼津駅、浜松駅は、ムーンライトながらの運転日だけは終夜で駅を開けておく必要があるのではないでしょうか。
JR東海が、1列車当たりの実質的な売り上げに対して、夜中に駅を開けておくためのコストをどう見るかが大きなポイントになりそうです。
「ムーンライトながら」は青春18きっぷの売り上げに貢献?
一方で、「ムーンライトながら」の存在は、青春18きっぷ自体の売り上げにかなり貢献している可能性もあります。
「ムーンライトながら」の運転区間は、東京~名古屋・京都・大阪を結ぶ大動脈の東海道本線ですので、そもそも需要自体はかなり大きいはずです。さらに、青春18きっぷで唯一乗車できる夜行列車です。青春18きっぷの旅で、夜間も移動しようとすると、ムーンライトながら以外の選択肢はありません。
このような点から、ムーンライトながらがあるから青春18きっぷを利用する、という方がそれなりにいるのではないかと想像できます。
鉄道に乗ることが目的の乗り鉄の方はともかく、青春18きっぷを格安の移動手段として利用するしている方は、ムーンライトながらがなくなったら、おそらく夜行高速バスに流れるでしょう。
列車単体でみるとあまりもうからないですし、運行のためのコストもかかる「ムーンライトながら」の運転を継続しているのは、青春18きっぷの売り上げにかなり貢献している、という判断があるのかもしれません。
格安旅行派に鉄道の選択肢を残す「最後の夜行快速列車」
夜行高速バスに対抗するために、各地で運転されていた夜行快速列車。次々と廃止されていき、2019年には「ムーンライト信州」(新宿→白馬)の運転もなくなってしまいました。
そんな中、唯一残っているのがムーンライトながらですが、この列車は、いわば、「最後の夜行快速列車」。青春18きっぷシーズンに格安で移動できる唯一の夜行列車となってしまいました。

ムーンライトながらが廃止されてしまったら、格安旅行派にとっては、長距離を鉄道で移動するという選択肢が事実上なくなってしまうでしょう。
もちろん、1日(2,370円相当)で東京から九州や青森まで行ける青春18きっぷの価格優位性は残りますが、よほど鉄道好きでないかぎりは、そんな修行のような乗り継ぎはしたくないでしょう。青春18きっぷ1日分の値段に、ちょっとプラスすれば、夜行高速バスで快適に移動できるわけですから。
185系引退時に「ムーンライトながら」はどうなる?
現在、ムーンライトながらは、JR東日本が所有する185系電車(10両編成)で運転されています。
185系は、現在、特急「踊り子」などに使用されていますが、中央本線の特急「あずさ」「かいじ」にE353系が投入されたことで、もともと中央本線の特急列車に利用されていたE257系を東海道本線へ転属する工事が実施されています。
そうなると、国鉄時代の古い車両である185系は引退、廃車となるでしょう。そのときに、ムーンライトながらはどうなるのでしょうか?

順当に行けば、E257系を利用する、ということになるのでしょう。ところが、車両を変更するためには、乗り入れ先となるJR東海の乗務員の訓練が必要になります。つまり、それなりにコストがかかるということです。
このタイミングで、ムーンライトながらが車両を変えて存続するのか、廃止になってしまうのか、判断がありそうです。
ポイントは、
- 乗客のほとんどが青春18きっぷを利用するもうからない列車
- 深夜時間帯の停車駅での客扱い対応が必要(しかも、すべてJR東海の駅)
という(特にJR東海にとっての)デメリットと、
- 青春18きっぷの売り上げに貢献している可能性がある
- 夜間の移動に鉄道という選択肢を残しておける
というメリットを天秤にかけたときに、どちらを取るのかということになりそうです。
JR東日本とJR東海の2社が絡んでいるので、両者ともに存続で一致するのかが重要ですね。
「夜行列車」の文化を継承する重要な列車
現在、JRの夜行列車は、定期列車としては寝台特急「サンライズ出雲・瀬戸」しか残っていません。コンスタントに運転される臨時列車を含めても、「ムーンライトながら」が加わるだけです。
かつて、夜通し運転される普通列車も多くありましたが、その流れを引き継ぐ列車は、大垣夜行にルーツを持つ「ムーンライトながら」しかありません。
利益云々を抜きにしても、昔ながらの夜行列車という文化を継承する重要な列車であることは間違いありません。

さらに、個人的には、「夜行列車」という文化時代を継承していくことが、JRにとっても重要なことではないかと考えています。というのも、「ななつ星in九州」や「四季島」のような豪華クルーズトレインに乗車するような方々は、おそらく、若いころに夜行列車で旅をしたの経験があるのではないかと思うからです。
ちょっと贅沢な海外旅行にも行けるような料金を払って、国内の鉄道の旅を選ぶわけですから、夜行列車にノスタルジーを感じているのではないでしょうか。
夜行列車で旅をしたことがない方が、中高年になったときに、さまざまな旅行の選択肢の中から、豪華クルーズトレインの旅を選ぶでしょうか。
そういう意味では、車両が変わったとしても、列車としては何とか運転を続けてもらいたいところですね。
以上、『年々運転日数が減る「ムーンライトながら」、JRにとっておいしくない列車は今後どうなる?』でした。正直なところ、列車単体でみると、JRにとってはデメリットのほうが多いのではないか、という気がしていますが、何とか運転を続けてほしいものですね。
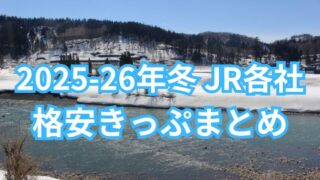
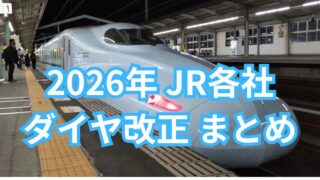
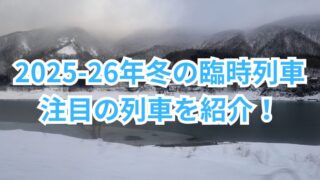
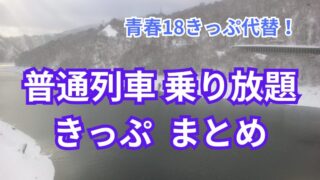

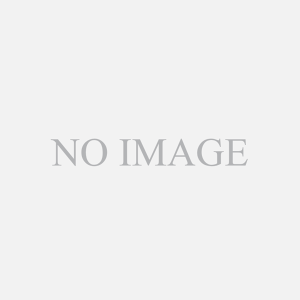
コメント
そして、ながらの指定券は転売野郎の餌食となり入手困難に。皮肉にもクルーズトレインの様に乗れたら相当幸運な列車になりました。利用者は乗れるかどうかわからないorプレ値で転売野郎から買う状態なので、鉄道好きでもない限り移動の選択肢に上がるとことも少なくなるかもしれません。高速バスに流れるのも当然の帰結かと。
昔のように近郊型車両で自由席の夜行の方が、むしろ多くの乗客を安く移動させることができ、メリットが多いように思えます。
ムーンライトながらはともかく、ムーンライト信州がなくなったのが地味に痛い。
朝イチ上高地に行くとか、朝イチアルペンルートに行くとか、朝イチ八方尾根に行くとか山・スキー関係が日帰りしづらくなったんですよね。
夏場・冬場に復活してほしいけど難しいでしょうね。
はつかりさん、コメントありがとうございます。
その通りなんですよね。あまりに運転日数が少ないと、プラチナチケットになってしまって、選択肢に上がらなくなってしまうんですよね。
お盆休みとかでなければ、いつでもだいたい乗れて、ほどほど混んでいる、くらいが交通機関としては理想なんですけどね。
くろふね (id:jranar)さん、コメントありがとうございます。
ムーンライト信州、何度か乗りましたが、夏場は登山の装備を持った人が多く乗っていました。
東武の尾瀬夜行みたいに、需要はあると思うんですけど、みすみす高速バスに取られてしまっているように思います。
ただ単に、JR東海が自社の車両で運行じゃないのがイヤなだけ。
別に普通の普通列車車両(ボックスシート車)で座席指定料金を請求すればよい。或いは立席扱いを実施して座席は整理料金(320円)を徴収するのも。これなら東海も自社の神領所属車で運行出来る。
普通列車で一部指定にすれば、普通運賃が取れる飛び乗り客が居るからそこから人件費を捻り出すのです。何も18客だけが対象では無いのが普通列車。
残念でありますが、これが現実であります。廃止の理由に「お客様の生活様式の変化」とありますが、ある意味間違いではなく、時代の変化や慣例で、そうさせてしまったと捉えられます。ネット記事や関連雑誌の記事で「JRは高速バスに負けた」と言う記事をよく目耳にしますが、これはJRグループ(以下、単にJR)は鉄道会社だけではなく、バス会社も全国にあります。このことからJRでは、夜間移動の主体を鉄道からバスへ移行したと考えられ、競合の場をレールから高速道路へと変えたと考えられます。これが後々慣例化し、既存事業者やツアーバス(当時※現在は既存事業者同様に路線バス事業者)などの競合の激化、更には車両維持や人員などのコスパの面からも考えられ、事実上夜間移動は高速バスにほぼ独り状態になったとしたうえで、バス同士の競合になった結果であります。つまり事実上夜間移動の選択肢は高速バスしかなく、その中でどの事業者を選ぶのかといった選択肢になります。これが慣例になり「生活様式の変化」になってしまったと言うことになります。JRでも日中は本業の鉄道を中心に、夜間移動はバスをメインに棲み分けをしたと考えられます。今回の「ムーンライトながら」の完全廃止もほぼ平行する高速バスの「ドリームなごや号」などにに移行を完了した捉えても間違いないでしょう。
abeken1763aさん、ご意見ありがとうございます。
鉄道だけでなく、高速バス、公共交通機関全体へ視野を広げてみると、ご指摘のとおりだと思います。
高速バスは、一時期のツアーバスの乱立で値下げ競争が激化していました。今では規制もあり、当時ほどではないにしても、大手のバス会社でも十分にムーンライトながらに勝てる料金設定ができるあたり、勝負あったということなのでしょうね。
そういう意味では、ムーンライトながらは、臨時化された時点で事実上終わっていたのでしょうね。よく今まで残してくれたな、という感じです。