神奈川県の工業地帯を走る「鶴見線」をご存知でしょうか? 大きな工場や物流倉庫が立ち並ぶ工業地帯への通勤路線ですが、朝晩のラッシュ時間帯を除くと、その様子はまさに「都会の秘境路線」。川崎や横浜といった東海道線の主要駅からすぐのところを走っているとはとても思えない路線です。
時間が止まったままの「国道駅」、昼間は列車がまったくやってこない「大川駅」、猫たちの住処になっている「扇町駅」そして、ホームから京浜運河越しの東京湾を眺められる絶景駅「海芝浦駅」。短距離の路線ながら、見どころ満載です。
この記事では、鶴見線の乗車記をお届けします。
鶴見線とは?
鶴見線は、鶴見駅を起点に、以下の3つの本線・支線からなるJR東日本の路線です。
- 鶴見~扇町(本線: 7.0km)
- 浅野~海芝浦(海芝浦支線: 1.7km)
- 武蔵白石~大川(大川支線: 1.0km)
本線の鶴見~扇町の路線から、海芝浦支線、大川支線が分岐する形になっています。
この地図のように、本線は鶴見川を渡って、首都高速横羽線と平行に進みます。その途中の浅野駅、武蔵白石駅から支線が分岐し、それぞれ埋立地の端まで行っています。本線はその先、浜川崎駅から運河を渡って扇町駅まで到達します。浜川崎駅は、南武線の支線(尻手~浜川崎)との接続駅です。
このように、鶴見線は、工場が立ち並ぶ埋立地の中を、運河を渡りながら進む路線なのです。
【鶴見線 乗車記1】都会の秘境路線で、国道駅、大川駅、扇町駅を訪問!
ということで、早速、鶴見線に乗ってみましょう。ここでは2018年に鶴見線に乗車したときの様子をお届けします。
※2018年当時の様子ですので、現在では変わっているところがあるかもしれません。その点はご了承ください。
頭端式の懐かしい鶴見駅のホーム

2018年4月のとある天気のよい土曜日、鶴見駅に到着したのは14時過ぎ。早速、鶴見線のホームに向かいます。
鶴見駅の京浜東北線のホームは地上にありますが、鶴見線は高架の2階にあります。途中、同じJR東日本の路線にもかかわらず、中間改札があります。鶴見線の他の駅がすべて無人駅で、簡易Suica改札機が置いてあるだけなので、この中間改札で乗車記録を確認しているのでしょうね。
※鶴見駅の中間改札は2022年3月に廃止されました。
鶴見線のホームは頭端式の2面2線。アーチ型の屋根が古めかしい雰囲気を醸し出しています。

鶴見線の電車は205系の3両編成。古くは山手線に投入され、通勤電車といえば205系! というほどの勢力を誇っていましたが、首都圏では次々と姿を消し、残っているのはここ鶴見線だけになってしまいました。
この205系、先頭車が「クモハ204形」という形式。長編成が多い首都圏では珍しい形式です。ク(制御車=運転台のある車両)、モ(電動車=モーターのある車両)、ハ(普通車)という意味ですが、編成が長い場合は、先頭車はモーターのない車両(「クハ」という形式)が多いのですよね。
昭和に取り残されたような「国道駅」
14時30分に鶴見駅を発車。7人がけのロングシートの1~2名程度とかなり空いています。
東海道線や京浜東北線、京急線の線路を超えて左にカーブすると、すぐに「国道(こくどう)駅」に到着。まずはこの国道駅を訪問します。

国道駅の改札は、鶴見線のホームの高架下にあります。この高架下、まるで数十年前から時間が止まってしまったかのような雰囲気を残しています。

営業していると思われる焼き鳥屋以外に、普通の民家と思われる家も数軒あるのですが、お住まいの方がいらっしゃるのかはわかりませんでした。
人通りは思ったよりも多いようです。国道へ抜ける近道として、日常的に利用されているようです。ただ、国道駅を利用する方は、ほとんど見かけませんでした。

国道駅の改札口です。自動券売機が一台と簡易Suica改札機があるだけです。当然のことながら無人駅ですが、この自動券売機の裏側は、かつては駅員室だったのかもしれません。

国道駅の高架下を抜けると、その横には国道15号線(別名:第一京浜)が走っています。クルマの通りはとても多く、至って普通の都市という感じ。国道駅の高架下に入ると、一気に昭和にタイムスリップしてしまったかのような錯覚に陥ります。

次の電車に乗るために、簡易Suica改札機にモバイルSuicaをタッチして入場します。階段の途中には、上り線と下り線のホームをつなぐ通路があります。先ほどの高架下のトンネルを横切っています。

通路から高架下を見下ろしてみました。右側に民家が並んでいますが、おそらく鶴見線の高架を造ったときに一緒に建てられたのでしょうね。高架に組み込まれてしまっているので、誰も住まなくなってしまっても、取り壊すことができないのでしょうか。
土休日は1日に電車3本!? 徒歩で訪れた「大川駅」(大川支線)

国道駅から、15時02分発の浜川崎行きの電車に乗車します。すぐに鶴見川を渡ると、次第に工場が増えてきます。15時10分着の武蔵白石駅で下車します。
武蔵白石駅は、大川支線との分岐駅です。その大川支線の終点、大川駅を目指すのですが、大川駅に行く電車は、土休日はなんと1日に3本だけ! 鶴見駅発07時10分、07時55分の次は、17時45分発まで、約10時間も電車がありません。仕方がないので、歩いて行こうというわけです。
※2023年現在、ダイヤは数分変わっていますが、土休日に1日3本しか列車がないことは変わっていません。
幸い、武蔵白石駅から大川駅までは約1km、徒歩でも15分ほどで到着します。

日中、大川駅へ向かおうとした人が時刻表を見て途方に暮れるのか、こんな張り紙までありました。要は、歩いて行けと……。

地図のとおり、武蔵白石駅を出て右へ進み、踏切を渡ります。しばらく行くと、運河を渡ります。
交通量はそれほど多いわけではないのですが、工業地帯ということもあり、行き交うクルマはみな大型のトラックで、ちょっと威圧感があります。歩道を歩いていれば安全です。

ということで、大川駅に到着しました。これまた、今にも朽ち果てそうな駅舎ですが、一応、毎日電車がやってくる、れっきとした駅です。

大川駅のすぐ先で線路は途切れています。その向こうには、日清製粉の大きな建物が。工場でしょうか。

大川駅のホームから。夕方まで電車は来ませんので、当たり前ですが、誰もいません。線路に並行している、先ほど歩いてきた道路には、大型のトラックが頻繁に行き来しています。ちょうどツツジがきれいに咲いていました。

大川駅のホームにもこんな掲示が。鉄道の駅なのに、近くのバス停を案内してしまっています(笑) どうしても電車に乗りたい人は、武蔵白石駅へどうぞ。
南武支線との乗り換え駅「浜川崎駅」

大川駅の訪問を終えて、武蔵白石駅に戻ってきました。上の写真は武蔵白石駅手前の大川支線の分岐です。右側へ行くと、先ほど徒歩で訪問した大川駅に着きます。

武蔵白石駅を15時50分に発車する浜川崎行きの電車に乗車します。わずか7分で終点の浜川崎駅に到着しました。
浜川崎駅は、鶴見線と南武支線の乗り換え駅です。南武線の本線は川崎~立川間を結ぶれっきとした通勤路線ですが、途中の尻手(しって)駅から浜川崎駅まで支線が伸びています。
浜川崎駅は、狭い道路を挟んで、鶴見線の駅と南武支線の駅が少し離れています。どちらも無人駅で、簡易Suica改札機が置いてあります。ただ、鶴見線と南武支線を乗り換える場合には、「簡易Suica改札機にタッチしないように」とアナウンスがありました。タッチしてしまうと、一度下車したことになって、料金の通算ができなくなってしまうのですね。

南武支線の電車がやってきました。2両編成の205系です。本線の方は、新しいE233系の6両編成の電車が走っていますが、支線のほうはワンマン化改造された205系です。
※南武支線の車両は、2023年、新潟地区で活躍していたE127系電車に置き換わる予定です。

南部支線のホームを見学し終えて鶴見線のホームに戻ってくると、扇町行きの列車が入ってきました。浜川崎駅の鶴見線のホームは、ご覧のようにとても幅が狭く、電車が入ってくると少し怖いくらいです。
鶴見線本線の終点駅「扇町駅」はネコ達の聖地?

浜川崎駅から乗車した16時13分発の扇町行きの電車。3両編成ですが、後ろの2両は誰も乗っていません。浜川崎駅でほとんどの乗客が下車してしまいました。100万都市の川崎を走る電車とはとても思えません。

浜川崎駅からわずか4分で終点の扇町駅に到着しました。周囲には工場が点在するだけの駅ですが……

そんな駅で出迎えてくれたのが、扇町駅の構内に住み着いていると思われるネコ達です。いい天気だったので、日陰の涼しいところでおやすみ中でした。

人を怖がることは全く無く、むしろネコのほうから近寄ってくるほどです。なんというか、人がいようがいまいがお構いなし!といった感じです。

この扇町駅に限らず、鶴見線の駅はネコが多いようですね。その中でも、扇町駅は、ネコスポットとして知られているようです。今回訪れたときには少なくとも5匹は確認できました。
【鶴見線 乗車記2】京浜運河越しの工場夜景が素晴らしい「海芝浦駅」を訪問
扇町駅からいったん鶴見駅に戻り、時間調整をして、もう一つの支線の終点「海芝浦駅」を目指します。今やフォトジェニックな駅として有名な海芝浦駅は、ホームから京浜運河越しに東京湾や工場を望むことができる駅です。「駅から出られない駅」でもあります。
浅野駅で海芝浦支線に乗り換え
扇町駅でネコ達と戯れたあと、いったん鶴見駅まで戻ってきました。1時間ほど駅前のドトールで休憩したあと、再び鶴見駅17時45分発の大川行きに乗車します。
そう、この列車は大川駅訪問のくだりで触れましたが、土休日は1日3本しかない大川駅に行くとても貴重な列車です。でも、目的地は大川駅ではありません。

海芝浦支線との分岐駅、浅野駅で下車します。
浅野駅は、上の写真のように、本線と海芝浦支線が分岐したあとにホームがあります。手前側のホームが海芝浦支線、右側のちょうど電車が入ってきたホームが本線です。

海芝浦行きの列車がやってきました。鶴見駅を17時52分、先ほど乗ってきた大川行きの7分後に出発する列車です。これに乗れば海芝浦まで乗り換えなしなのですが、浅野駅を見てみたかったので、1本早い列車に乗ったのでした。
駅から出られない駅「海芝浦駅」

浅野駅から2駅、わずか4分で終点の海芝浦駅に到着です。
この海芝浦駅は「駅から出られない駅」としても有名です。駅のすぐ横には東芝の事業所があります。改札を一歩出ると、そこは東芝の私有地のため、東芝の社員や関係者の方しか駅を出ることができないというわけです。
ちなみに、ホーム上に「出場」「入場」と書かれた簡易Suica改札機があります。海芝浦駅を訪問してから戻るときには、「出場」のほうにタッチしてから、「入場」のほうにタッチすればOKです。
ホームの先にある「海芝公園」からの絶景!

ホームの先(改札内)には、「海芝公園」という小さな公園が整備されています。海や工場の絶景を見に来る観光客のために東芝が整備してくれた公園。無料で開放してくれています。ありがたいことですね。
海芝公園のすぐ横は東京湾につながる運河です。その向こうには、首都高速湾岸線の「鶴見つばさ橋」や大黒ふ頭にある「大黒PA」、それに、工場群を眺めることができます。

だいぶ日が暮れてきました。鶴見駅で時間調整したのは、夕暮れどきに海芝浦駅を訪問したかったからです。日没時刻と時刻表を見比べて、乗る列車を選んだのでした。
上の写真が、首都高速湾岸線の「鶴見つばさ橋」です。湾岸線はたくさんの運河を越えて埋立地を結んでいるので、このような橋がたくさんありますね。

日没の時刻を過ぎました。首都高速の橋や周囲の工場群の灯りが目立ってきました。左奥の明るいところは、大黒ふ頭にある大黒PAのようですね。
海芝浦駅のホームからの眺めも最高!

海芝浦駅に次の電車がやってきました。この折返し列車に乗って帰りますが、まだ20分ほど時間がありますので、ホームからの夜景を楽しみます。

だんだんと暗くなり、鶴見つばさ橋の横にある工場の夜景もサマになってきました。とはいえ、運河を挟んでいるので、工場は小さくしか見えません。工場夜景だけを目的にするのはいまいちかもしれません。ここは、運河と工場、高速道路など、臨海地域の風景を楽しむ場所でしょう。
ちなみに、Googleマップによると、この工場のような建物、東京ガスと昭和シェル石油が共同出資して設立した「(株)扇島パワー」という会社のLNG火力発電所のようです。

大黒ふ頭方面は目立って明るい印象です。首都高速湾岸線と大黒線の複雑なジャンクションがあり、その真ん中がパーキングエリアになっています。

鶴見つばさ橋より東側も、少し明かりが見えますが、何があるのかわかるほどではありません。再びGoogleマップさんに尋ねると、JFEスチールの工場か、扇島太陽光発電所のようです。

まもなく18時50分発の鶴見行きの電車の発車時刻です。最後に人の少なくなったホームと電車、海をフレームに入れてパチリ。
その後、鶴見線、京浜東北線などを乗り継いで帰宅しました。
以上、『【鶴見線】工業地帯を走る都会の秘境路線、時間が止まった「国道駅」、猫の住処「扇町駅」、海の絶景駅「海芝浦駅」など見どころ満載!』でした。都市や住宅街から近いながら、工業地帯を走るために沿線の住人が極端に少ない鶴見線。複雑に枝分かれした支線の終着駅は、それぞれ味のある面白い駅ばかりです。鶴見線の魅力的な駅を訪問し、最後に海芝浦駅で海を眺めるのがおすすめです。
関連記事
当ブログでおすすめの路線や列車、沿線の観光スポットなどをエリアごと、ジャンルごとに紹介しているページです。筆者が各地の観光列車やローカル線に乗車した時の乗車記をまとめています。沿線の観光スポットやお得なきっぷについての情報も紹介しています。鉄道旅行・乗り鉄の際の参考にぜひご覧ください!


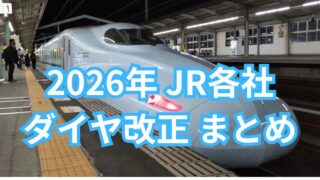
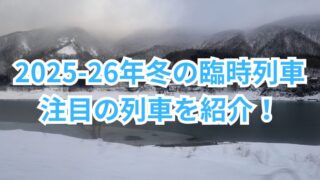
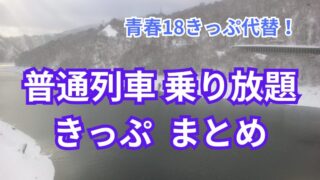


コメント