日本は山が多い国ですので、山間部を走る鉄道路線はたくさんあります。今回は、その中から「高原」っぽい車窓が眺められる路線を4つ、独断と偏見で選んでご紹介します。いずれも車窓が素晴らしく、景色を眺めながらのんびりと旅をするのにピッタリの路線です。ぜひ、青春18きっぷの旅で乗りに行ってみてください。
八ヶ岳と野辺山高原の車窓が素晴らしい「小海線」(小淵沢~小諸)

小海線は、山梨県の小淵沢駅と、長野県の小諸駅を結ぶ、全長78.9kmの非電化ローカル線です。「八ヶ岳高原線」 という愛称のとおり、八ヶ岳の東麓を南北に走っています。標高の高いJR駅トップ10のうち、実に9駅が小海線の駅という、まさに日本を代表する高原路線です。
小海線ではどんな絶景が見られるの?
小海線の車窓は変化に富んでいます。
まず、小淵沢駅を出ると、いきなり急勾配を駆け上がっていきます。小淵沢駅の時点で標高は881メートルもありますが、そこからさらに登っていくわけです。しばらく森の中を進むため、眺望はよくありません。ところどころ、木々の合間から八ヶ岳が見られる程度です。

清里駅を出てしばらくすると、これまで絶え間なくうなりを上げていたエンジン音がふと止んで、急に視界が開けてきます。このあたりがJR線の最高地点です。この車窓の劇的な変化が小海線のハイライトです。私はこの車窓の変化が大好きで、小海線には数えきれないほど乗車しています。
このJR最高地点から野辺山~信濃川上~佐久広瀬の3駅間くらいが、高原鉄道の名にふさわしい車窓が望めます。天気が良ければ、車窓の西側に八ヶ岳をくっきりと眺めることができます。
小海線乗車のおすすめプランは?
ぜひ、小淵沢駅からの乗車をおすすめします。八ヶ岳を眺めたいのであれば進行方向左側(西側)に座りましょう。急勾配を登り切り、パッと視界が開けたときの美しさは忘れられません。
小海線では、小淵沢~野辺山間の区間列車も設定されていますので、途中の清里駅や野辺山駅で途中下車して、散策や観光を楽しむのもおすすめです。特に、夏場であれば野辺山周辺での観光がおすすめです。標高は1,300メートル以上あり、真夏でも気温は30℃に届かずさわやかな気候です。天気がよければ、駅前のレンタサイクルで自転車を借りて、小海線の線路沿いを走ってみることをおすすめします。JR線の最高地点には、最高地点の碑が建っています。野辺山駅から約2kmですので、自転車でしたらすぐです。

さらに、2017年から運転を開始した小海線の観光列車「HIGH RAIL 1375」もおすすめです。大きな窓にゆったりとした座席で小海線の車窓を楽しむことができます。事前に予約しておくと、車内でお弁当やスイーツを受け取ることができるサービスもありますし、小淵沢駅で駅弁やおやつ、飲み物などを購入してから乗車するのもいいですね。
「HIGH RAIL 1375」については、以下の紹介記事をご覧ください。日中運転の「HIGH RAIL 1号」「HIGH RAIL 2号」と夜間運転の「HIGH RAIL 星空」の乗車レポートもあります。

小海線については、以下のページで関連記事をまとめていますので、ぜひご覧ください。小海線の車窓や沿線の観光スポット、「HIGH RAIL 1375」の乗り比べなど、盛りだくさんの内容になっています。

実は屈指の山岳路線!「中央本線」(東京~塩尻)
前述の小海線にアクセスするために利用する中央本線(JR東日本の東京~塩尻間)も、高原路線といってもよい路線です。
東京の街中を走る「中央線」(東京~高尾)にしか乗ったことがないと意外に思われるかもしれませんが、中央本線は立派な山岳路線。小海線との接続駅、小淵沢駅の標高は886メートル、中央本線で最も標高の高い駅となる富士見駅は955メートルもあるのです。
中央本線ではどんな絶景が見られるの?
東京側から下り列車に乗ると、高尾駅までは関東平野の中を直線的に進んでいきますが、高尾駅を出ると一気に山の中へと入っていきます。徐々に標高を上げていきますが、大月駅の周辺以外は、あまり視界が開けていません。

見どころの一つが、東京・山梨の都県境付近にある山間部を抜けて、甲府盆地へ入るところです。勝沼ぶどう郷駅の少し手前ぐらいから、一気に視界が開け、甲府盆地とその向こうの南アルプスの山々が車窓を彩ります。

甲府盆地に向けて標高を下げたあと、甲府駅を出ると、再び標高を上げていきます。車窓を見ていると、かなりの登り坂になっているのがわかります。
そして、右手には八ヶ岳が見えてきます。小海線に乗ればもっと近くで眺めることもできますが、中央本線の小淵沢周辺からでも、八つの頂を持つといわれる八ヶ岳の山並みをしっかり見ることができます。
上の写真は小淵沢駅の展望台から撮影したものですが、車窓からも同様に見ることができます。
中央本線乗車のおすすめプランは?
旅程にもよりますが、東京側から甲府・松本方面への下り列車がおすすめです。どんどん標高を上げて行ったり、甲府盆地に入ると一気に視界が開けたりと、車窓の展開がドラマチックです。
青春18きっぷを利用する場合には、基本的に高尾で乗り換えが必要です。中央本線には、高尾~松本間を走破する長距離普通列車が1日に何本かあります。また、東京や新宿から乗り換えなしでアクセスできる大月からも、松本方面への列車が出ています。詳しくは、以下の記事をご覧ください。
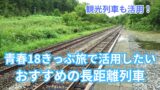
長距離を走る普通列車が多い中央本線ですが、中でも、高尾~長野を5時間近くかけて走破する「441M」(列車番号)という列車があります。5時間と聞くと長いように感じるかもしれませんが、この「441M」は、途中での特急列車の通過待ちが少なく、かなり速い部類に入ります。チャンスがあれば利用してみてください。
高尾発長野行きの普通列車「441M」については、以下の記事で紹介しています。
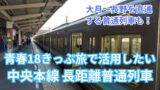
運転日は月に1日ほどと少ないですが、青春18きっぷ+指定席券で乗車できる観光列車「リゾートビュー諏訪湖」が、長野~富士見間で運転されています。中央本線でもっとも標高の高い駅、富士見駅から乗車することができます。中央本線で松本・長野方面へ向かうには良い列車です。
「リゾートビュー諏訪湖」の運転日やダイヤ等については、以下の乗車記をご覧ください。

岩手山の車窓が素晴らしい「花輪線」(好摩~大館)
花輪線は、岩手県盛岡市の好摩駅から、秋田県大館市の大舘駅までを結ぶ、全長106.9kmの非電化ローカル線です。「十和田八幡平四季彩ライン」 という愛称のとおり、八幡平のすそ野をぐるりとまわるように走っています。
花輪線の列車は、基本的に盛岡~大館間を通しで運転されています。盛岡~好摩間は、東北新幹線の八戸延伸開業時に、第三セクターの「IGRいわて銀河鉄道」に転換された区間ですので、青春18きっぷでは乗車できません。盛岡駅から乗車する場合には、別途、660円のきっぷを購入しておきましょう。
花輪線ではどんな絶景が見られるの?

盛岡駅から乗車すると、好摩駅までの区間では、車窓左側に岩手山を見ることができます。岩手山は、東側から見ると、富士山のようにすそ野の広い美しい独立峰に見えます。標高2000メートルを超える山で、山体も大きいので、その存在感は抜群です。
好摩駅を出ると、いわて銀河鉄道線(旧東北本線)から分かれて北西へ進路をとります。このあたりは内陸の田園風景といった感じですが、途中の松尾八幡平駅を出たあたりから急勾配を登り始めます。
昔は、この急勾配を超えるために、SLの三重連(SLの機関車を三つ連結した編成のこと)が見られたところで、それだけ勾配が急なところです。現在の気動車のパワーであれば全く問題はないですが、それでもエンジン全開で、スピードを落として登っていきます。田園風景から一気に急勾配を駆け上がるこのあたりが、ハイライトの一つでしょう。
急勾配を登り切ったあたりが、安比高原駅です。安比高原駅から湯瀬温泉駅あたりまでは、比較的標高の高い盆地状のところを走行します。小海線ほど視界が開けているわけではないですが、高原列車といってもよい区間です。
花輪線乗車のおすすめプランは?

非電化路線の場合は、急勾配を登るほうが楽しいので、盛岡駅から大館方面行きに乗車 するのがおすすめです。岩手山や八幡平は車窓の左側に見えますので、進行方向左側の座席を確保しましょう。
花輪線には、キハ110系というJR東日本の非電化路線でよく見られる気動車が走っています。私が以前乗車したときには、キハ58系という古い気動車が走っていて、冷房が付いていませんでした。それでも、窓を全開にしているとさわやかな風が吹き込んできて、気持ちよかったものです。今の列車は窓が開かないのが残念ですね。
阿蘇の雄大なカルデラを走る「豊肥本線」(大分~熊本)

豊肥本線は、大分駅と熊本駅を結ぶ148kmの路線です。九州のほぼ真ん中を東西に横切る路線です。熊本側の熊本~肥後大津間は電化されていて、熊本市中心部の近郊路線となっています。それ以外の区間は非電化で、ローカル線の雰囲気が漂う路線です。
豊肥本線ではどんな絶景が見られるの?
豊肥本線の車窓の見どころは、阿蘇の巨大カルデラの外輪山を抜ける険しい区間と、カルデラ内部を走る平坦な区間の変化でしょう。
熊本駅から乗車すると、肥後大津駅までは都市部を走ります。都会の近郊路線といった雰囲気です。肥後大津駅から非電化区間に入ると、一気にローカル線の雰囲気が濃くなり、田園風景の中、次第に高度を上げていきます。

前半の最大の見どころは、立野駅のスイッチバック です。阿蘇の外輪山が途切れたあたりに位置していて、鉄道、道路、川までもが、立野あたりからカルデラの内外を結んでいます。険しい外輪山が唯一途切れたところを狙って、鉄道や道路を敷設したのでしょう。
立野駅でスイッチバックして、さらに標高を上げてカルデラの内部へと入っていきます。カルデラの内部は、まるで盆地のように平坦な地形になっていて、先ほどまでの外輪山の険しい地形が嘘のようです。周囲は、車窓左側に外輪山、右側には阿蘇山の本体である阿蘇五岳が望めます。どちらを見ても山で、ここが巨大なカルデラの中であることが実感できます。
阿蘇観光の拠点駅の阿蘇駅や宮地駅を過ぎると、再び外輪山を抜けるために高度を上げていきます。今度は、外輪山の低いところをめがけて蛇行し、長いトンネルを抜けて外輪山の外へと出ていきます。途中、阿蘇のカルデラ内を一望できるところもあり、世界的にもまれなカルデラ内の街並みを眺めることができます。
【番外編】代行バスからの雄大な車窓が素晴らしい「根室本線」(落合~新得 代行バス)
最後に、番外編として、根室本線の落合~新得間をご紹介します。
この区間は、狩勝峠という峠越えの区間になっています。狩勝峠の車窓からは、十勝平野を一望することができ、その雄大な車窓から、「日本三大車窓」の一つになっていました。

現在は新線に付け替えられてしまったため、かつてほどの車窓ではなくなってしまいましたが、それでも、北海道のスケールを感じられます。
なぜ【番外編】にしたかというと、この区間、現在は列車が走っていないためです。
2016年の台風被害の影響で、2023年5月現在も、東鹿越~新得間が不通になったままです。この不通区間を含む富良野~新得間は、2024年3月末で鉄道を廃止、バス転換されることが決まっています。JR北海道はすでに国土交通省に廃止届を提出しています。

鉄道が廃止となっても、代替となる路線バスを利用すれば旅をすることはできますが、「根室本線」として青春18きっぷで乗車できるのは2024年3月までとなります。

不通区間の東鹿越~新得間では代行バスが運転されています。実は、この代行バスが、かつての狩勝峠越えの旧線に近いルートを通ります。景色のよいところには展望台やレストハウスがあるのですが、残念ながら代行バスは通過してしまいます。それでも、代行バスの車窓からは、一瞬ですが、雄大な十勝平野の絶景を見ることができます。
この区間を含む富良野~新得間の乗車記を以下のページに掲載していますでの、ぜひご覧ください。

以上、独断と偏見で高原路線(高原っぽい車窓が見られる路線)を4つ紹介してみました。単なる峠越えだけではなく、高原の雰囲気が味わえる路線を選んでみましたが、いかがでしたでしょうか? いずれも青春18きっぷで乗車できる路線ですので、乗り鉄や鉄道旅行の参考にしてもらえればと思います。
関連記事
本記事で紹介している高原の路線だけでなく、海が見える絶景路線、川沿いの路線など、車窓から見える景色ごとに、おすすめの路線を紹介しています。青春18きっぷの旅で、車窓が素晴らしい路線に乗ってみたい!という方は、ぜひご覧ください。
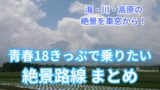
青春18きっぷ関連のトップページです。青春18きっぷの最新情報や基礎知識、おすすめの路線や列車、使いこなしのコツなど、さまざまなコンテンツを掲載しています。ぜひご覧ください。


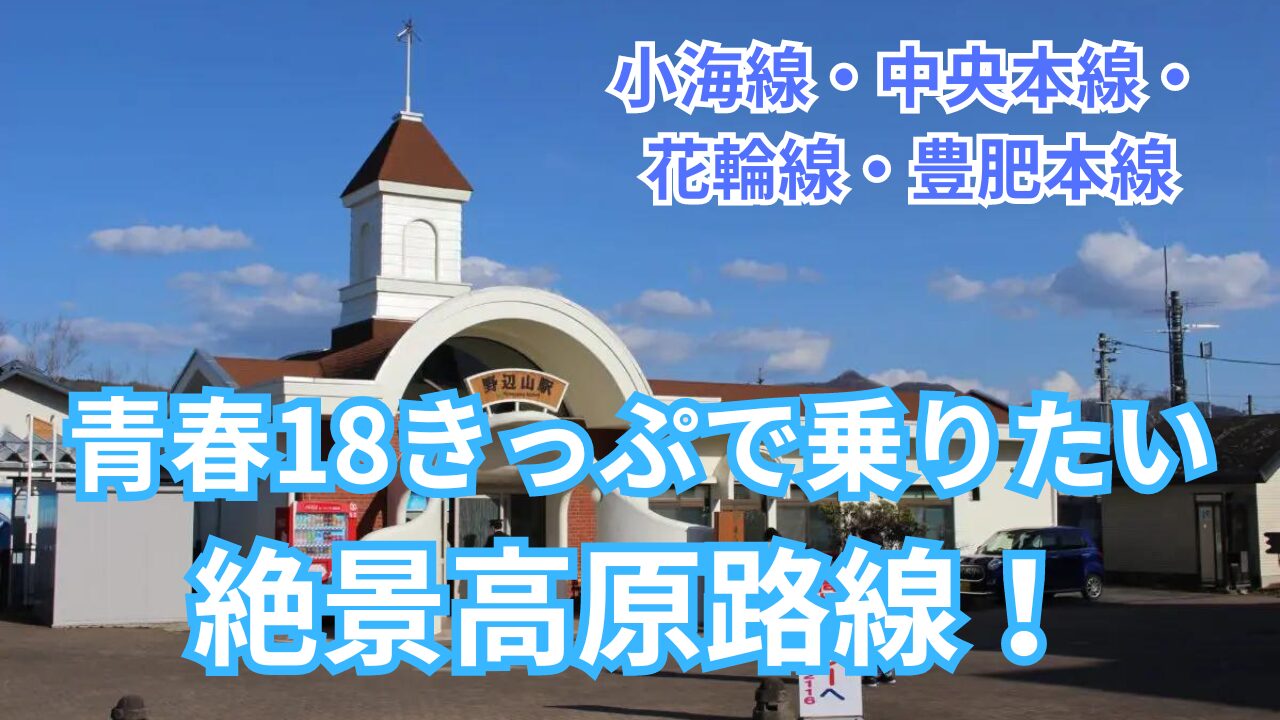

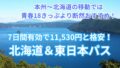
コメント